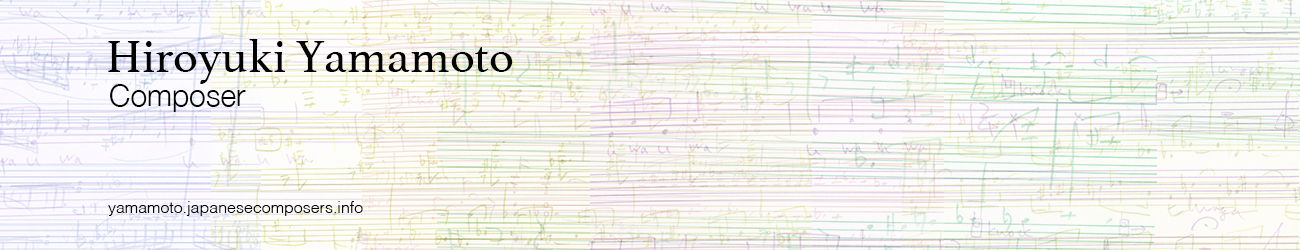《エミリからの手紙》が初演されます
The vocal ensemble piece, Letters from Emily (text by Emily Dickinson) will be premiered by Vox Humana in Tokyo on 21 March 2024.
ヴォーカルアンサンブル作品を7年ぶりに書かせていただきました。《エミリからの手紙》の初演は3月21日です。
先鋭的なヴォーカル集団、ヴォクスマーナの他に、西川竜太さんが率いる女声合唱団「暁」、クール・ゼフィールにはかつて《失われたテキストを求めて》というシリーズの曲を書かせていただきました。《失われた〜》の楽譜は「器」のようなもので、演奏者が自由にテキストを探し出して、スコアの指示に従ってはめ込んで歌う、というものです。なのでこれは私と演奏者の共同作業によって毎回違うものが作られる感じです。
このアイデアは、そもそも音楽(の作曲)がテキストに左右されることに抵抗を感じていたことから生まれたものです。テキストの内容あるいは構造が、作曲以前に用意されていると、作曲がテキストの支配下に置かれてしまって何ともやりにくいのです。
《失われた〜》ではどんなものが出来上がってくるのか自分にもわからないという愉しみがあるので、我ながらこのアイデアには満足していました。しかしそうするとそろそろ逆の、つまり従来的な、既存のテキストに「歌を付ける」という声楽曲を不思議と書きたくなってくるものです。

今回の新作は、19世紀のアメリカの詩人、エミリ・ディキンスンEmily Dickinson(1830-1886)のテキストを使用しています。E.ディキンスンについては多くの作曲家やアーティストが影響を受けて作品を生み出しているので、実は今さら感がないわけではありません。ただ、私が使ったのは彼女の詩ではなく、彼女が人々に宛てて書いた手紙です。ディキンソンは生涯をかけてとんでもない分量の手紙(特に若い頃の手紙は長文が多い)を書いていて、その中から4通の手紙を選んで作曲しました。
なぜ詩ではなく手紙なのか? というと、単純に私が興味を持ったのは彼女の詩よりも手紙だったからです。一般的に手紙というのは人にモノを伝えるという機能を持っているものですが、E.ディキンスンの手紙にはなんというか、本気で伝える気がないのかもしれないと思えるような、曖昧すぎる表現や意味不明な語句などに充ちているものがあり(もちろん明確に意図がはっきりしている手紙もたくさんあるのですが)、またその中に彼女らしい、隠喩に充ちた詩が含まれていることも珍しくありません。
なぜそのような不思議な手紙を人に宛てて書いたのでしょうか。私にはそれらの手紙が人に宛てているというよりも、彼女にとっては手紙を書くことそのものが自身の生活や人生にとって重要な行為であり、それは必ずしも受け取り手のことを重視していなかったのではないか、と思えてしまいます。ディキンスンはいまでいう「引きこもり」で、家に会いに来た人とさえ手紙でやり取りをしたという逸話もあるほど人とのコミュニケーションが独特であり、また決して得意ではなかったようです。このような彼女特有の特性から、現代ではE.ディキンスンが自閉スペクトラム症(以下、自閉症)であったとする研究者がいます。たとえば「いつも白い服を着ていた」というエピソードは、ルーティーンに陥りがちな自閉症の特性と見て取れるということのようです。
自閉症は、その字面から「自分の殻に閉じこもっている」というネガティヴな印象を与えます。しかしどちらかというと「他人と異なる自分の世界を持っている」という方がおそらく近くて、場合によっては閉じこもるどころか「自分の世界」を広く公開する行為に出ることもあります。たとえば同じ文学者だとアンデルセンやルイス・キャロルも自閉症だったといわれていますが、彼らはディキンスンのように引きこもってはおらず、むしろ他人との社交に積極的だったようです(ただし独特な方法によってですが)。そして自閉症が問題になるとしたら、それはその人自身に問題があるというのではなく、周囲や社会との相対的な関係性において、軋轢や問題が生じることが多いという状況そのものが自閉症を自閉症たらしめている、と考えることが適切というのが現在の考え方のようです。もっともE.ディキンスンの特性は、周囲との「難しい関係」を引き起こすと同時に、素晴らしい詩作ももたらしており、それは周囲との直接的な関係性とは違うところで起きているので、自閉症の捉え方には多面性があるといえるのかもしれません。1
「自分独自の世界を持つ」自閉症は、文学者や画家など創作を生業として成功した人に比較的多かったのではないかという印象を個人的には持っています。しかしディキンスンやアンデルセンやルイス・キャロルの各人が自閉症だとしても、その顕れの様子がまったく違うことも珍しくなく、「自閉症とはこういう人だ」と一概にいうことはできません。いずれにせよ、「自分の世界を持っている」……別の言い方をすると「人と違う世界を見ている」という部分については、多くの自閉症の人に当てはまるようで、私はそこに美学的な関心を持ち、その例としてディキンスンの書く奇妙な手紙に惹かれたわけです。
これまでの私の声楽作品とはだいぶ違うアプローチで書いた曲につき、今回は文が長くなりました。しかし同日の稲森さんの委嘱曲が30分を越える作品らしいので、この日は聴きごたえバッチリです。ちなみに《エミリからの手紙》に微分音はありません。
ヴォクスマーナ第51回定期演奏会
2024年 3月21日(木)19:00開演
豊洲シビックセンターホール
一般3000円(当日3500円)、大学生1500円、高校生以下1000円
チケットご予約フォーム
お問合わせ ryuta0530nishikawa@gmail.com
※山本もチケットをお預かりしています。
プログラム
山本裕之(b.1967)/ エミリからの手紙(委嘱新作・初演) 詩:Emily Dickinson
稲森安太己(b.1978)/ L’amor, l’alchimia e la pedantaria 愛と錬金術と衒学と(委嘱新作・初演)
渋谷由香(b.1981)/「黒い森から」12声のための(2016委嘱作品・再演) 詩:佐峰 存
小出稚子(b.1982)/ the smoke of kreteks(2018委嘱作品・再演)
伊左治直(b.1968)/ アンコールピース27委嘱新作・初演
- ただし最近、自閉症などの「発達障害」を人間の特異な能力、つまり「天才性」と安易に結びつける人がいますが、それはメディアによるミスリードと私は感じています。実際、自閉スペクトラム症の「スペクトラム(連続体)」という言葉が表すように、「普通の人」(定型発達)と自閉症の人はグレーゾーン(非定型)を挟んでシームレスに繋がっており、境界を明確に規定するのは難しく、そのため定型発達の人でも感覚過敏や興味の範囲が狭いといった自閉症的な症状を持つことはよくあります ↩︎