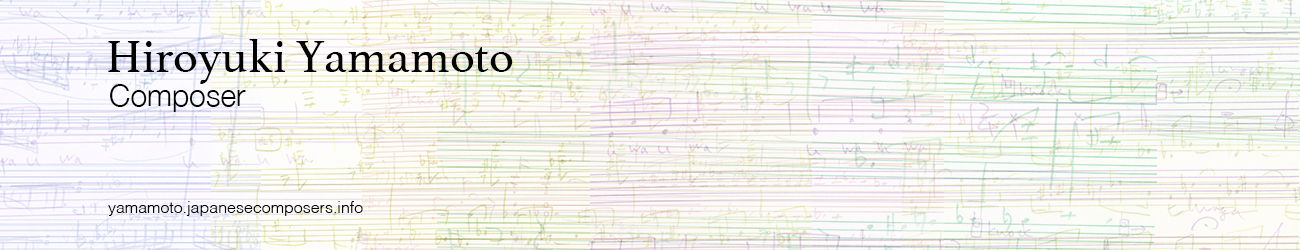Phidias Trioによる“Re-invent”(終了御礼)
昨年の個展と違い、今回私は主催者ではなかったので運営には携わらずにおり、演奏もPhidias Trioという現代音楽のスペシャリストだったので、大船に乗った気分でおりました。
演奏された作品については過去の三つの記事(その1)(その2)(その3)に詳しく書きましたが、すべて私の作品で構成されるプログラムとなりました。依頼者である勇気のあるPhidias Trioには尊敬を禁じ得ません。








Phidias Trioの公演では最後に演奏者の軽いトークがあるのですが、「最初から最後まで4分音」という話があり、あらためてそれが私の、少なくともここ20年ばかりのスタイルを象徴したものなのだと認識しました。
今回のメインである《わしらの新しいご領主に…そして税金を払う岩手の農民たち》はバッハの《農民カンタータ BWB 212》のリコンポジション(再作曲)であり、バッハをどのように「こちら側」に引きずり込むのかが作曲家としての力の見せ所のような気持ちがありました。J.S.バッハの音楽は数多の作曲家たちが扱ってきたものですが、バッハの音楽が持つ強さ故に「バッハ感」を引き剥がすのが難しいと誰もが感じていると思います。たとえばWebernが手がけた《6声のリチェルカーレ》のように、その人固有の中心的技法(彼の場合は「点描書法))をもってしてようやくリコンポジションが成立する、そのようなレベルの作曲家がJ.S.バッハなのだと考えてきました。
4分音を「衝突」させるのは、私の微分音の使用スタイル(いわば芸風)であると考えているので、それを積極的に使うのはもちろんですが、半音階的な転調も今回頻繁に使用しています。調性音楽のリコンポジションのときはほぼ必ず使用してきた手法ですが、これについてはなかなか触れてくる人はいません。実はこの手法は、「音楽の曖昧性」を調性レベルで具現化する目的で、4分を積極的に使う以前から使用してきたものです。前の記事では書かなかったことなのでここに書き足しておきます。
4分音と半音転調、そして前の記事でも書いた「機能を排除した調的和音」が、《わしらの〜》でバッハをこちら側に引っ張る主な三つの手法だったのですが、それがどれほど上手くいったのかは客観的に判断できません。ただこれらによって演奏の困難さが増えたであろうことは想像に難くありません。特に自分が声楽家だったらいやだな、と単純に思うと思うのですが、今回のお二人(坂口真由さん、牧山亮さん)はそれらを素晴らしくコントロールされていました。声楽パートに4分音はないものの、器楽でしっかり鳴らされているので相対的なピッチコントロールは容易ではなかったと思います。ちなみに九州出身のお二人ですが、東北訛りをかなりリアルに(もちろん美声で)再現されていました。
本公演の感想を詳しくブログに書かれた方がいたのでリンクを貼らせていただきます。
https://note.com/modochan/n/n9c33b642d583
https://jun-yamamoto.hatenablog.com/entry/2025/12/27/130002
年末のお忙しいときに足をお運びいただいた皆様には感謝しております。